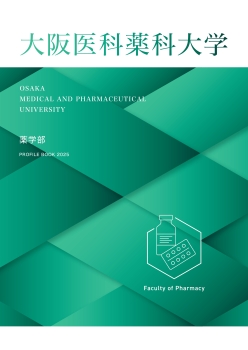2020年度は、終始コロナ禍に翻弄される中、夏から冬にかけて、学生たちに心動かされることがありました。
日本薬学会関西支部では、薬局と大学が連携し、将来地域医療の中核を担う薬剤師となるような学生を育てたいという望みを込め、「在宅医療推進教育プログラム: HOPE (HOme care Promotion Education program」を実施しています。学生が在宅医療の現場で学ぶこともあり、一時中止も検討されたが、結局、感染対策に万全を期して実施することになりました。
参加は各大学の任意とされ、本学も積極的な募集は敢えて行いませんでした。ところが、例年より反響が大きく、「今こそ地域で薬剤師に何ができるかを学びたい」と参加を希望する学生が相次ぎました。想定外の展開に、学生の意識変化を垣間見た感がありましたが、参加した学生から提出された報告書を一読した瞬間、深い洞察と患者に寄り添う本質を突く内容に、感動と共に成長を確信しました。
-

EPISODEエピソード
学生から「薬剤師が地域でなにができるのか」と声があがった
薬学部 社会薬学・薬局管理学研究室
恩田 光子おんだ みつこ
-

EPISODEエピソード
薬剤師だけにとどまらない未来
「薬学部に入学して将来は薬剤師として働く」という意思をもって入学する学生がほとんどかもしれません。実際に、本学部新卒者の80%ほどの学生が薬剤師資格を使って医療現場で働いております。しかし、6年間という年月の中で、将来の進路に対して気持ちが変わってしまう学生もいます。
私の研究室では、そんな気持ちを抱えた学生の新たな夢を応援しています。製薬企業の研究職を目指すというのは正直厳しいですが、研究室での活動を充実させることによって、多数の学生が国内外の学会で研究成果を発表し、実際に製薬企業の品質管理職・生産技術職・学術職・開発職、あるいは公務員などに就職している先輩が多数おります。教員として、配属学生が希望する企業や自治体の内定をもらって嬉しそうな顔を見せてくれるとき喜びを感じています。
薬学部 製剤設計学研究室
戸塚 裕一とづか ゆういち
-
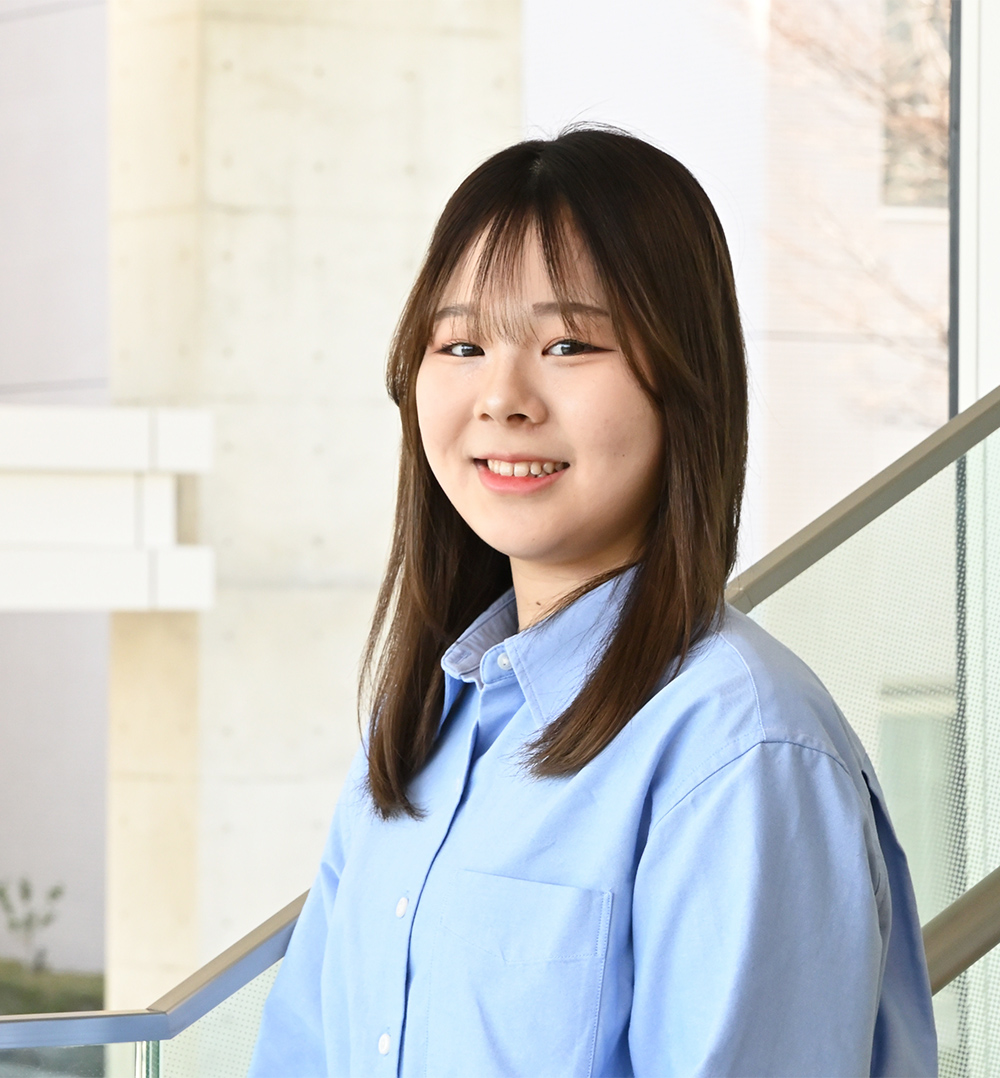
EPISODEエピソード
早い目標設定から有意義な学生生活を送る
幅広い知識を持ち、患者さんに寄り添い、ともに考えられる薬剤師になりたいと思い薬学部を選択しました。
本学の薬学部は、国家試験合格率が高く、多職種連携教育により薬学の領域を越えた医療従事者としての教養を身につけることができます。また、カリキュラムの改訂により、新たに「薬学連携演習」という授業が増えました。有機化学と生薬学を関連づけた授業や各科目で学んだ知識を統合的に活用し課題に取り組むことでより深い理解につながります。
早期体験学習、病院実習など、1年生から様々な経験ができます。6年間で身につけておきたいことや、学んでおきたいこと、将来どんな薬剤師になりたいかなど早い段階から目標を立てることが可能です。有意義な学生生活を送ることができるのも本学の強みだと思います。
薬学の勉強は思っていた以上に大変ですが、その分達成感ややりがいを感じることができます。
薬学部(2024年度入学)
高田 莉沙たかだ りさ
-

EPISODEエピソード
アスリートとして、薬学生として
「なぜ薬を飲めば病気が治るのか」
この疑問が医療分野に関心を抱くようになった原点です。
私は5歳から水泳を始め、インターハイでの入賞やオリンピック選考会への出場といった経験を重ねてきました。しかし、医薬品やドーピングに関する知識が十分でなかったため、痛み止めやサプリメントの摂取に不安を感じることが少なくありませんでした。もし当時、正しい知識に基づいて適切な助言を与えてくれる存在が身近にいたなら、より安心して競技に打ち込めたのではないかと感じています。
このような経験から、私は同じような悩みを抱えるアスリートを支えられる薬剤師になりたいと考え、本学薬学部への進学を決めました。
本学での実習では、座学で得た知識を自らの手で確かめる機会が豊富にあり、理解が一層深まるとともに、物事をより高い解像度で捉えられるようになります。特に薬理学において薬の作用機序を学んだ際には、薬学を学ぶ意義を強く実感します。
薬学の学びは高度かつ困難を伴うものですが、熱心に指導してくださる教授陣や志を同じくする仲間の存在に支えられ、日々充実した学生生活を送っています。
薬学部(2023年度入学)
木下 翔真きのした しょうま
大阪医科薬科大学の学びの特徴は、研究だけでなく臨床にも重きが置かれていること。
これからの薬学は調剤だけでなく、臨床の現場で活用されてこそ意味があるとの考えからです。
医学部・看護学部があり、また大学病院を持つ大阪医科薬科大学だからこそ、多職種との連携や「薬を使用する患者さま」と実際にお会いしながら学ぶことができます。
こうした経験は、今社会に必要な薬学人がどのようなものかを考えるきっかけを生み出します。
NEWS
薬学部のお知らせを見る未来に届く学びがある
学びの特徴
人を知り学びを積む
6年間の学び
-
第1
学年薬学を学ぶ基礎力と、豊かな人間性と知性を養うために、1年次のカリキュラムは、数学、物理学、化学、生物学など基礎学習や各種語学、人文科学系の教養科目が大半を占めます。そこに「薬学入門」「基礎細胞生物学」などの基礎薬学科目、「薬用植物学」などの応用薬学科目、「基礎有機化学実習」などの実験科目が加わります。大学での基本的な学習方法を指導する「アカデミックスキル」や、4月と9月に地域の病院、薬局、ドラッグストア等を見学する「早期体験学習」といったカリキュラムも用意されています。幅広い基礎能力を磨く1年です。
-
第2
学年薬学専門教育の土台となる基礎薬学科目を中心に学びながら、「生薬学」「衛生薬学」などの応用薬学科目、「薬理学」「薬物治療学」などの医療薬学科目へと学びを深化させていきます。さらに「漢方・生薬学実習」「分析化学実習」「物理化学実習」など、本格的な実習・実験科目もスタート。1年かけて、自然科学全般と薬学の関係をしっかりと認識しながら、薬学の専門家となるための準備を積み重ねていきます。
-
第3
学年これまでカリキュラムの中心にあった基礎教育科目と基礎薬学科目は数科目に絞られ、代わって「医薬品化学」「分子細胞生物学」「物理薬剤学」などの応用薬学科目と、「製剤設計学」「薬物速度論」などの医療薬学科目が学習のメインとなります。さらに実習も大きく増え、4年次からスタートする研究室や臨床的学習に備えた技術や実践的知識の修得が本格化します。また医薬品に関する情報管理を学ぶ「医薬品情報学」や、「生命医療倫理」「医薬と法」など、医薬品を社会や制度から考える科目もスタート。徐々に視野を広げる1年となります。
-
第4
学年これまで学んできた基礎知識を、実際の臨床や実験へ応用展開していくことが、4年次の学習の柱となります。特に5年次に行われる病院・薬局での実務実習に向け、徹底した実務実習事前学習が行われます。処方箋と調剤、疑義照会、医薬品の管理と供給、服薬指導と薬剤管理指導、医薬品の安全基準など、薬剤師業務全般について実習、演習、講義形式で確実に学びます。さらに全員が研究室に所属し、自身の興味関心に基づいた研究活動も開始。受け身の学びから能動的学習へと大きく転換します。
-
第5
学年5カ月半の病院・薬局実務実習では、病院および薬局における薬剤師の業務と責任を理解し、チーム医療や地域医療に参画するための調剤、服薬指導、医薬品の供給・管理などを、実際の医療現場で学びます。さまざまな症例に接し、患者さん、あるいは医師や看護師から医薬品に関する質問を受けたら、どのように対応すればいいのか。教科書だけでは決して学べない臨床体験を通じて、薬剤師に期待される役割を体感、獲得します。実習以外の時間は、研究室での実験・研究にあてられます。6年次の研究発表・卒業論文執筆に向けて、こちらも追い込みをかけていく時期となります。
-
第6
学年6年間の学びの集大成とも言える薬剤師国家試験の合格に向けて、集中学習を実施します。薬剤師国家試験の出題基準に基づいた講義・演習を受けることで、単なる試験合格だけでなく「社会に求められる薬剤師」として活躍できる実力を養います。さらに所属する研究室で取り組んできた研究テーマについて、論文をまとめ、成果発 表を行います。医学部・看護学部と合同開講する「多職種融合ゼミ(連携)」に参加すれば、実践的なチーム医療の模擬体験も可能です。悔いのない最終学年を過ごし、社会に出てからも大いに活躍してもらえるよう、全学を挙げてサポートを行います。