3月28日〜30日、北九州国際会議場で開催された第101回日本生理学会大会のポスター発表の部で、本学医学部生が発表を行いました。
■医学部 5年生 德野 隼暉さん(生理学教室学生研究員)
演題:アセチルコリン受容体εサブユニット欠損ゼブラフィッシュを用いた運動能の推移に関する解析
ゼブラフィッシュの神経筋接合部では、速筋・遅筋それぞれに投射する運動神経の性質が異なり、筋収縮に重要なアセチルコリン受容体のサブユニットの構成も異なります。速筋特異的なアセチルコリン受容体に発現するεサブユニットを欠損させたゼブラフィッシュの系統 (ε KO) では、成長過程で速筋に投射していた運動神経が遅筋に投射を換える、「シナプスつなぎ換え現象」が当研究室の研究で示唆されましたが、そのメカニズムは未解明です。
本研究では、このシナプスつなぎ換えが起こる時期を特定するため、ε KOを用いて日齢ごとの運動能の推移を解析しました。その結果、ε KO は12 日齢頃から運動能が低下し、21日齢には運動能が回復することがわかりました。このことから、ε KOの一部の個体では12日齢頃からシナプスつなぎ換えが起こり始め、21日齢頃には完了することが示唆されました。
今後、蛍光タンパク質を運動神経に発現させた系統を用いたライブイメージングでシナプスつなぎ換え現象を可視化する予定です。
-

生理学教室の中城光琴 助教(左端)らと懇親会の会場にて -
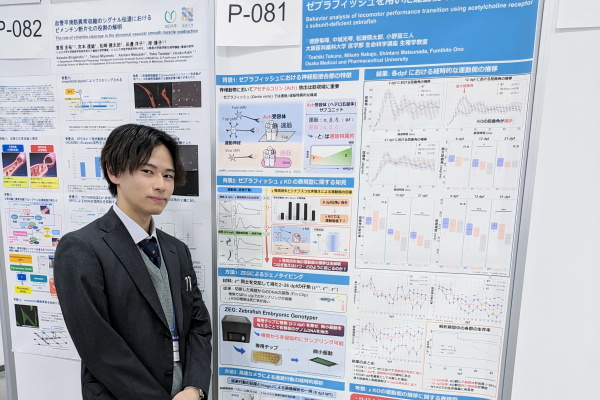
発表ポスター前の德野隼暉さん -
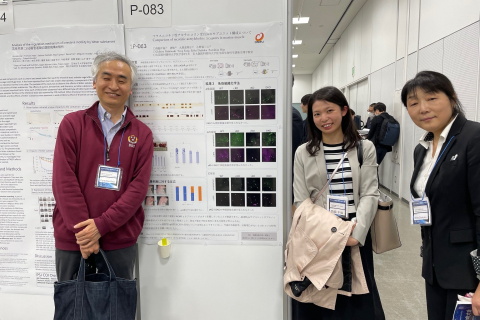
左から小野富三人 教授、西脇千紘さん、大黒恵理子 講師(准)
■医学部4年生 西脇 千紘さん(生理学教室学生研究員)
演題:マウスニコチン性アセチルコリン受容体のサブユニット構成について
神経からの運動指令を筋肉へ伝えるアセチルコリン受容体には、遅筋型と速筋型があることがゼブラフィッシュで初めて明らかになり、この違いが哺乳類にも存在するのかを知るためにマウスで実験を行いました。
発表に向けて実験結果をまとめ、どのように伝えると分かりやすいかを考えることで、改善点や追加する点に気づきました。そして自分の発表をすることで研究内容を客観的にみることができ、今までやっていたことを振り返る良い機会になりました。また、異なる分野の研究をされている方々のお話をたくさんお聞きし、とても勉強にもなりました。
これからは今まで以上に頑張っていきたいと思います。