在宅看護学領域では、健康問題や障がいをかかえながら、在宅で暮らしている人々と家族がその人らしい生活を送ることができるよう支援することをめざして、在宅ケア方法を探求し、サポートネットワークの構築、在宅ケアシステムの改善・開発に関する教育および研究を行っています。在宅看護では、対象の「生活者」の視点を尊重し、判断力、また限られた条件のなかでエビデンスにもとづいたケアができる実践力と創造力、他職種との連携やコーディネート力が求められます。めまぐるしく変化する社会情勢の中で、療養者とその家族がその人らしい生活を送るために私たちに求められる役割や課題について共に考えていきましょう。
授業風景


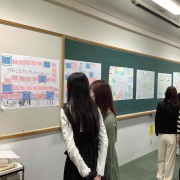
【呼吸器装着体験(演習)】 【地域・在宅看護論(グループワーク)】 【訪問体験-療養者への情報収集-(演習)】
【3年生】在宅看護学援助方法:呼吸器・酸素機器管理が必要な療養者の看護
実習(高知県)
多職種連携地域医療実習
2023年度(4年生)
-

【地域包括支援センターでの訪問】
-

【地域住民の長生きの秘訣 ミニデイで一緒に体操】
-

【地区踏査で展望台まで登山】
2024年度(4年生)
-

【ミニデイでいきいき100歳体操に参加】
-

【いきいきふれあいセンターで健康の秘訣を調査】
-

【汗見川診療所を見学】
海外との交流
【台北医科大学(台湾)の実習生への実習指導・交流会】
地域・社会との交流
【元気いっぱいサロンでの講演・交流】
授業科目
地域・在宅看護論、地域在宅ケア実習(2022年度~)、在宅看護学概論、在宅看護学援助論、在宅看護学援助方法、在宅看護学実習、統合看護学実習、卒業演習
メンバー紹介
教授 | 真継和子 KAZUKO MATSUGI

主な研究テーマは、在宅療養者の家族支援や看護倫理についてです。人と人とがかかわる時そこに何が生じているのかについて関心があり、現在、在宅療養者とその家族の生活体験に焦点をあてながら、どのような支援が必要なのかについて研究しています。なかでも家族支援に焦点をあてながら、人と人とのつながりを大切にした「ケア共同体」の構築を模索しています。また、看護者の倫理的実践能力の向上をめざし、組織の倫理という観点からあらためて現場の実践の状況を調査し、現実に即した倫理教育プログラムの開発を行っています。
今後は、訪問看護師の卓越した看護実践を可視化するとともに、訪問看護師の看護実践や教育実践の質評価を行いながら、訪問看護の質向上に向けた研究を行っていきたいと考えています。
准教授 | 大橋尚弘 TAKAHIRO OHASHI
 腎移植後、在宅での生活を行っているドナーやレシピエントへの長期的、継続的なフォローアップに関する研究を行っています。今後は、訪問看護師の教育や訪問看護を取り巻くシステムについての研究を行い、利用者や家族が本当の意味で満足して訪問看護を利用できるようにしていきたいと考えています。
腎移植後、在宅での生活を行っているドナーやレシピエントへの長期的、継続的なフォローアップに関する研究を行っています。今後は、訪問看護師の教育や訪問看護を取り巻くシステムについての研究を行い、利用者や家族が本当の意味で満足して訪問看護を利用できるようにしていきたいと考えています。researchmap.jp/masachiko
准教授| 伊藤真理 MARI ITO

長年クリティカルケア看護を担ってきた私はプライマリ・ケアに関心を持ち、在宅看護の世界に飛び込みました。プライマリ・ケアとは、さまざまな環境や患者、家族、コミュニティとの持続的な関係を通じて、個人の健康とウェルネスのニーズの大部分に対応する責任を負う多職種チームによる全人的、統合的、アクセス可能、公平なヘルスケアの提供と定義されています(Implementing High-Quality Primary Care: Rebuilding the Foundation of Health Care,2021)。人と人がつながり合う地域を住民の皆様と一緒につくり上げ、困っていてもSOSを出せない人の力になれるように尽力したいと思います。結果として、救急搬送されるその一歩も二歩も手前で、健康破綻を食い止めることができればうれしいです。一緒にプライマリ・ケアにおける高度実践看護を追究しませんか。
助手 | 有吉真里菜 MARINA ARIYOSHI

2017年に本学を卒業し、附属病院で働く中で自分が行ってきた退院支援が本人や家族の気持ちに寄り添えているのか疑問を持つようになりました。また、これから在宅で暮らす本人やそれを支える家族にとって必要な支援とは何かと考えるようになり、その後は回復期リハビリテーション病棟や訪問看護の現場で退院支援について学んできました。臨床の経験を生かし、在宅看護についての学びに役立てたいと考えています。
社会貢献活動・その他の取り組み
研究会の紹介
NPO法人SEANが主催する「生きがい工房 元気いっぱいサロン」で、高齢者を対象とした健康講座を行っています。また、2016年4月から、大学-地域-病院協働型の健康支援活動としての、「いきいきプロジェクトcocokara」を発足し、サロン活動を展開しています。また、在宅看護研究会を発足し、臨床の方々と一緒に事例検討や研究活動を行っていきます。
2024年度の卒業研究のテーマ
●「在宅療養中の認知症高齢者のBPSDによる家族の介護負担に対する家族支援に関する文献検討」
●「在宅療養者のインタビュー調査からみる患者・家族の思いに沿った退院支援に関する文献検討」
●「高齢者の退院における意思決定に関する文献レビュー」
●「排泄介助を必要とする在宅療養者の家族負担を軽減するための看護支援」
●「在宅介護者の疲労感を判断する際の尺度および観察点に関する文献検討」
●「在宅看取りをする家族が抱く困難に関する文献検討」
●「高齢糖尿病患者の食事療法自己管理に関連する要因についての文献レビュー」
●「療養者との死別体験が訪問看護師に及ぼす心理的影響と対処」
2023年度の卒業研究のテーマ
●「アドバンス・ケア・プランニングにおいて看護師が抱える困難に関する文献検討」
●「看取りケアにおける若手看護師の困難に関する文献検討」
●「在宅重症心身障害児の父親が役割を遂行する上での困難:文献検討」
●「小児の渡航心臓移植期間における患児及び家族のニーズと看護援助に関する文献検討」
●「Ⅱ型糖尿病患者のQOLに影響を与える要因に関する文献検討」
●「在宅療養をしている認知症高齢者の家族の介護負担の要因に関する文献検討」
●「精神科病棟における退院支援に関する文献検討」
カテゴリー別卒業研究テーマ一覧(2020年度-2022年度)
●認知症関連
•「認知症高齢者の在宅療養生活継続に影響する要因についての文献レビュー」(2022)
•「若年性認知症療養者の在宅介護継続を可能とした家族介護者の要因について—若年性認知症をもつ高齢者を介護する配偶者へのインタビューを通して—」(2022)
•「認知症患者の骨折前後におけるADLに関する文献検討」(2020)
●神経難病関連(ALS等)
•「ALS患者の心理的状態と心理的サポートに関する文献検討」(2021)
•「神経難病療養者の心理社会的QOLに影響を及ぼす要因と支援についての文献レビュー」(2020)
●がん関連
•「在宅療養期にある終末期がん患者の家族が抱える困難についての文献レビュー」(2022)
•「小児がんの子どもが抱える復学に対する思いに関する文献検討」(2021)
●高齢者ケア
•「ひとりで暮らす要介護高齢者の生活実態に関する文献検討」(2022)
•「在宅高齢療養者を介護する家族の家族内役割分担に関する文献検討」(2020)
●小児・医療的ケア児
•「自宅で生活している医療的ケア児の発達支援に関する文献検討」(2021)
•「NICUから在宅療養を目指す子どもを持つ家族の在宅移行期に抱える困難」(2020)
•「重症心身障害児童をもつ母親の療育上の原動力に関する文献レビュー」(2020)
●訪問看護師
•「家族介護者による高齢者虐待に対する訪問看護師の看護実践:事例研究」(2022)
•「積極的治療継続を望む終末期高齢がん療養者の思いを実現する訪問看護師の看護実践」(2022)
•「在宅療養継続を可能にした訪問看護師の看護支援」(2022)
•「新人訪問看護師に求められる実践能力及びそれに対する教育的課題」(2021)
•「ALS療養者の希望する生活を実現するための訪問看護師の実践」(2021)
●その他
•「脊髄損傷のある療養者の1事例を通して」(2022)
•「麻痺障害を抱える壮年期脳血管疾患患者の職業復帰に関する文献検討」(2021)
•「人工膝関節全置換術後高齢者の運動機能と生活に関する文献検討」(2021)
•「脳血管障害後遺症のある療養者の家族介護者への支援に関する文献検討」(2020)
•「消化管ストーマ保有高齢者のスキントラブルへのセルフケア支援に関する文献検討」(2020)
•「在宅療養者の服薬アドヒアランス向上に向けた多職種連携の実態に関する文献検討」(2020)


