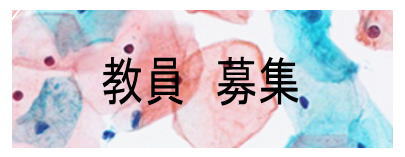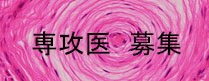研究について
消化管腫瘍、尿路腫瘍、頭頚部腫瘍、婦人科腫瘍などにおける病理学的研究を幅広く行っています。それらの研究プロジェクトは、臨床科との良好な連携・協力のもとに共同研究の形で実施されているものが少なくありません。歴史的には肝臓・下垂体・軟部腫瘍の病理学的研究も盛んであり、私たち教室の研究テーマとしては「腫瘍発生・診断」がキーワードになるでしょう。以下に、最近の代表的な研究業績を挙げます。
★ Expression of Preferentially Expressed Antigen in Melanoma, a Cancer/Testis
Antigen, in Carcinoma In Situ of the Urinary Tract. Fujii S, et al. Diagnostics
(Basel). 2023.
尿路上皮内癌におけるPRAME(悪性黒色腫の診断に有用なマーカー)発現の意義について論じています。なお、本研究の一部は、医学部3~4年の学生研究コースにおいて、配属学生(Fujii
Sくん)が実施してくれました。
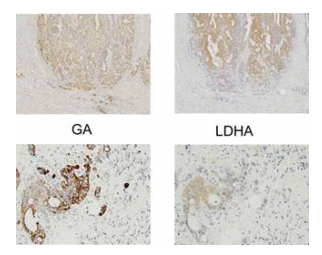
★ Intratumoral heterogeneity of glutaminase and lactate dehydrogenase
A protein expression in colorectal cancer. Mizuno Y, et al. Oncol Lett,
2020.
pT3大腸癌99症例の腫瘍先進部をターゲットとして、代謝系酵素のglutaminase(GA)、LDHA等の免疫組織化学的検索を行ったところ、がんの悪性化や転移に関連するとされているbudding部位に一致してGA発現亢進、LDHA発現低下が確認されました。この結果は、GAやLDHAといった代謝系酵素が、腫瘍先進部での浸潤転移に役割を成す可能性を示唆します。
また、学部生に研究環境を提供する目的で、学生研究員の受け入れも行っています。研究に興味をもつ学生有志が、病理学的手法を用いてがんの研究を行っています(放課後、週2回程度)。興味とやる気がある学生の参加を希望します。
教育について

医学部教育として、2学年で「病気の成り立ち1」コース(病理学総論の講義および実習)、3学年で「病気の成り立ち2」コース(病理学各論の講義)、4学年で診断学コース(病理解剖/CPC関連の講義、など)を担当しています。また、3学年での「学生研究」コースでは、毎年6名ほどの学生が配属されています。
研修医教育にも力を入れており、初期研修の選択科として病理研修を引き受けています(年度平均で、のべ5名ほどが選択・研修実績あり)。研修内容としては、まずは研修医の進路・興味等をよく聞いたうえで、病理部に提出された病理検体の肉眼観察、切出し、診断業務を主体として行います。その方策としては、OJTの考え方を基本として、上級医とのマンツーマン体制により実施します。
また、課外活動にはなりますが、学部生におけるactive learningを推進する目的で、MGH症例輪読会を行っています。学生有志が小グループで行っている勉強会(月2回程度)で、医学用語に英語で慣れ親しむには最適! 興味とやる気がある学生の参加を希望します。
教室の歴史&沿革
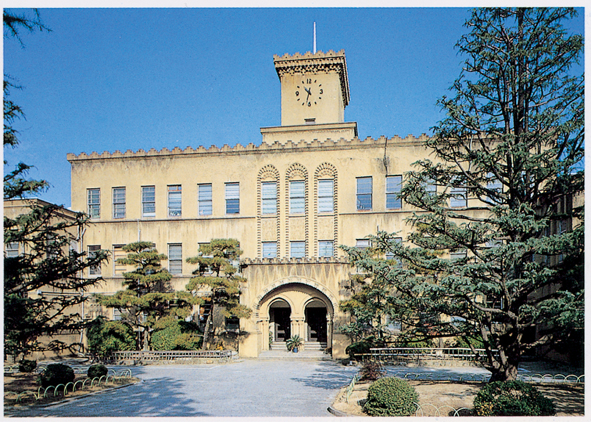

私たち大阪医科大学病理学教室は、その源を辿ると本学創立直後の1928年にさかのぼり、およそ九十年余に渡る長い歴史と伝統を持ちます。
初代教授は江口季雄先生(1928~1946在任)で、その後、波多野輔久先生(1951~1954在任)、田部浩先生(1954~1968在任)へと引き継がれました。田部先生が着任してまもなく、当時助教授であった濱本祐二先生が教授に就任(1955~1986在任)し、田部第一病理、濱本第二病理の二教室体制となりました。その後、第一病理の教授は中田勝次先生(1973~1994在任)、芝山雄老先生(1994~2013在任)が担当し、第二病理の教授は森浩志先生(1986~2008在任)へと引き継がれています。森浩志先生の定年退官時には学内で大講座化が進められており、その流れの中で前述の二教室と後述の病院病理部は2008年に一つの組織母体として統合されました。統合により生まれた「病理学教室」は、教室教授(chairperson)となった芝山雄老先生の下に、病院病理部担当として辻求専門教授(2008~2016在任)、教育・剖検担当として岡田仁克専門教授(2008~2019在任)を置く体制となりました。その後、2013年8月には廣瀬善信先生が教室教授として着任し、現在に至っています。
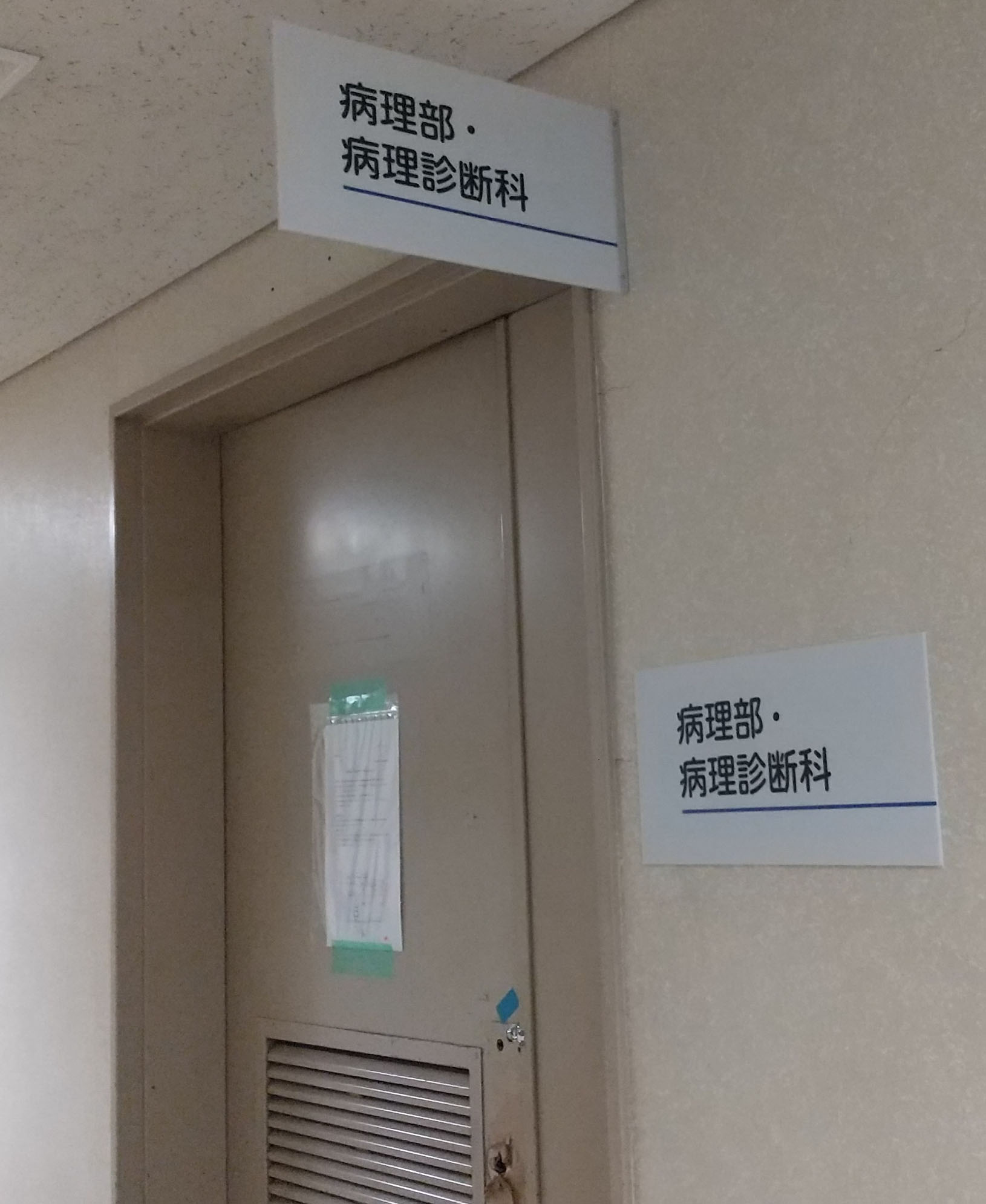

附属病院に目を転じますと、1959年に中央臨床検査科(1976年に中央検査部へと改組)が発足しました。それまでの臨床検査は各臨床科が独自に行っていたようですが、中央臨床検査科が生まれた後はその病理部門が中央診療部門として病理業務を行うことになりました。病理診断の担い手としては、当初は第一病理の中田先生をはじめとするスタッフのみでしたが、1986年の森教授の就任以来、第二病理のスタッフも参加するようになりました。1989年に堤啓先生(1989~2001在任)が中央検査部病理部門専任の助教授(その後、診療教授)として就任し、病理部門と病理学教室の協力のもと病院病理業務がさらに充実しました。2001年に中央検査部病理部門は病院病理部として組織替えし、病理部長として辻求先生(2001~2016在任、2008年から専門教授)が担当しました。前述のように2008年に運営上は「病理学教室」に統合されましたが、院内では引き続き病院病理部として業務が行われました。2014年からは「病理部・病理診断科」を標榜し、2016年には栗栖義賢先生が病理診断科長に着任し、現在に至っています。