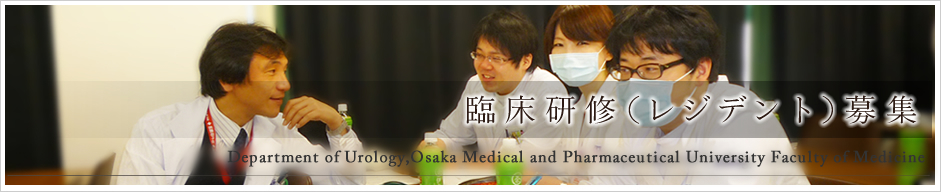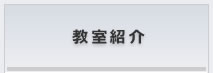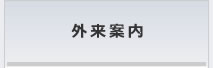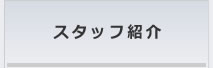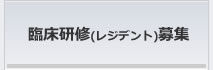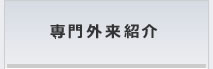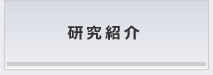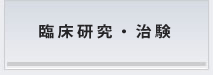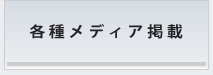���₢���킹 contact
��569-8686�@
���{���Ύs��w��2-7
TEL�@
072-683-1221�i��\�j
���җl�ցA�����k�͊O������f���Ă��������B
�Տ����C(���W�f���g)��W
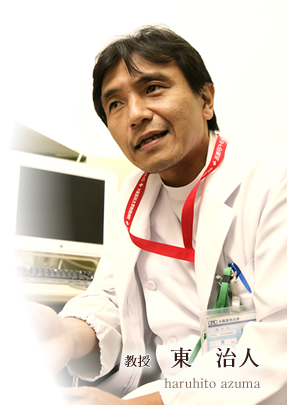

�����Љ�̂Ƃ���ł����b���܂������A�������́u�����߂����Â̎��H�v����ɔO���ɒu���āA�g���җl�Ɋ���A�������Áh�@���ɑ�����A��Ȃɓ����I�Ȏ��Â̊J���ƒɎ��g��ł��܂��B�Ⴆ�ΗՏ��ł́A�ʏ�̓����厡�Âɔ������Ȃ��Ȃ����i�s���O���B���ɑ������厮�����剻�w�Ö@�i�O���A�����ɂ�銳�҂ɗD�������Áj�̊J���Ȃǂ��A���̑�\��ł��B�����ł͊����Â̌��_�Ƃ������ׂ��u���]�ڂ̃��J�j�Y����͂Ǝ��Áv�A�����āA�ڐA�̈�ɂ�����u�Ɖu�}���܂��g�p���Ȃ��ڐA�F�V�K�Ɖu���e�̗U���@�̊J���v�Ɏ��g�݁A�����̗Տ����p�Ɍ����ē���w�͂𑱂��Ă��܂��B
����ɂ��ẮH�@��{�I�ȃR���Z�v�g�́u�����߂����w����v�ł��B���Ȃ킿�A�g�w�Ԃׂ��{�l���������߂Ă���̂��H�h�@���X�̃X�^�b�t�ƃR�~���j�P�[�V�������[���ɂƂ��āu�j�[�Y�ɂ��Ȃ���w����v�̎�����ڎw���Ă��܂��B �@
��A��Ȃ͇@��p�I�ȊO�Ȏ��ÁA�A���ː����ÂƂ̃R���{�ɂ����ː����ÁA�����āA�B���t���́A�������́A�t�ڐA���܂߂������t�s�S�ɑ��鑍���I��ÂȂǁA��舵�������̎�ނ�͈͂��ɂ߂čL���A���ɉ�X�̋����͂���������i��Â���|���Ă���̂ŁA�u���A���߂���Ő�[��Áv���K�����邱�Ƃ��\�ł��B
�X�^�b�t����̂��b�������ڗđR���Ǝv���܂����A�O�Ȉ�Ƃ��Ă̘r���čō��̗Տ����ڎw�������搶�A���邢�́A�C�O���w���o�����ăA�J�f�~�b�N�ȓ��ŋ��߂����搶�A���邢�́A�����J�ƈ�Ƃ��Ēn���Âɍv�����邱�Ƃ�ڎw���Ă���搶�A���邢�́A�����̑S�Ă��o��������Ō��߂悤�Ǝv���Ă���搶�A�ǂ�Ȑ搶�ł��K����]�ɉ����������J���邱�Ƃ��m�܂��B
���W�f���g����̊�{�p���b��p�Ǘᐔ�b�֘A�{�� �b �C�O���w�̂������b ���C��̐搶���ւ̃��b�Z�[�W
����L�����A�v���O�����b �w���E���C��̊F���܂�
���W�f���g����̊�{�p��

�ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A�w�Ԃׂ��{�l���������߂Ă���̂��H���[���ɔc�����A���含�Ɛϋɐ��������o������V�X�e�����\�z���邱�Ƃł���ƍl���Ă��܂��B�{�l����̓I�ɁA���H�Ŋw�ԑ��ヌ�W�f���g����V�X�e���A���Ȃ킿�A�f�f�A��p���܂߂����ÁA�����āA�t�H���[�A�b�v�Ƃ�����������f�Â����W�f���g����̓I�ɏC�w����V�X�e�����\�z���A�^��Ɩ��_�������ōl���A�𖾂���A���Ƃɂ���Ď��含�Ɛϋɐ��������o�����Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
��p����B����ő�̋ߓ��͎�p���������邱�ƁI
��p��Z�̏K���Ɋւ��āA��X�́A��p����B����ő�̋ߓ��͎�p���������邱�ƁI�ł���ƍl���Ă��܂��B��p�O�ɂ͎�p���ŕ�����I�ł��傤���A��p��ɂ͐�y��w����̎�p�̌������ς��܂��I��y�ƁA�ǂ����Ⴄ�̂��H�ƍl���邱�Ƃɂ���ă��`�x�[�V�����A�b�v�ɂȂ���܂��B
�����A�������N�̕��o���Z�p�F���̍��i���͂���߂č����A�Z�p�I�ɔ��ɍ������x�����ێ����Ă��܂��B�@�܂��A�N��700��̎�p���������Ȃ��ɂ́A���̃V�X�e�������ɗL�p�ł���A�Ⴂ�͂����̂܂ܑg�D�̗͂ƂȂ��Ă��܂��B
��p�Ǘᐔ
�p�@�� |
��p����(��) |
| �O���B������ᇎ�p�F�i���{�b�g�x���O���B�S�E�p�iRALP�j�j | 77 |
| �t�i�A�ǁj������ᇎ�p�F�i���o���j | 24 |
| �t�i�A�ǁj������ᇎ�p�F�i�J���j | 3 |
| �t�i�A�ǁj������ᇎ�p�F�i���{�b�g�x���t�����؏��p�iRAPN�j�j | 45 |
| ���t�E�o�p�F�i���o���j | 2 |
| �A�Nj������F(LRV���܂�) | 169 |
| ���o�����t`����p�F�i���{�b�g�x���t`���p�j | 3 |
| �N��������ᇎ�p�F�i�����؏��j�i�J���j | 1 |
| �N��������ᇎ�p�F�i�S�E�j�i���{�b�g�x���N���S�E�p�iRARC�j�j | 8 |
| �N��������ᇎ�p�F�i�S�E�j�i�A�ǔ畆ᑁj | 1 |
| �A�ǔ畆ᑑ��ݏp�F�i�A�H�ύX�p�̂݁j | 1 |
| �N��������ᇎ�p�F�i�o�A���I��p�i�����͊w�f�f���܂ށj | 159 |
| �N��������ᇎ�p�F�i�o�A���I��p�i�����͊w�f�f���܂܂Ȃ��j�j | 22 |
| �o�A���I�N���Ìŏp | 10 |
| �A���ǐ؏��p�F�i�J���j | 1 |
| �o�A���I�O���B�؏��p | 19 |
| �㕠��������ᇎ�p | 3 |
| �o�A���I�A�H���Ώ����p�F�i���[�U�[�g�p�j | 42 |
| �o�A���I�N�����ΓE�o�p�F�i���[�U�[�g�p�j | 4 |
| �o��I�t�i�t᱁jᑑ��ݏp | 32 |
| �o��I�t�X�E���h�p | 1 |
| ���V�����g�ݒu�p�F�i���Ȍ��ǎg�p�j | 78 |
| ���V�����g�ݒu�p�F�i�O���t�g�g�p�j | 4 |
| ���̐t�ڐA�p | 8 |
| �ڐA�t�̎�p | 8 |
| �A���g�s�������p�J�e�[�e�����o�����u�p | 13 |
| �O�A����ᇐ؏��p | 1 |
| ��s��p�i��؊J�p�j | 2 |
| �A�s������ᇎ�p | 2 |
| ����������ᇎ�p | 6 |
| �����P�]��p | 5 |
| �����O����p�i���������D���p�j | 1 |
| �A�X������p | 8 |
| �����Ö�ᎍ����p | 3 |
| BOAI | 54 |
| ���̑� | 155 |
�֘A�{��
| �a�@�� | �a���� | �Ζ��̐� |
| ����a�@ | �X�U�X�� | ��� |
| �T�c�����a�@ | �X�P�V�� | ��� |
| ���{�ϐ���Õa�@ | �V�V�W�� | ��� |
| �É��ϐ�����a�@ | �U�R�R�� | ��� |
| ���m��Εa�@ | �S�V�V�� | ��� |
| �͓������a�@ | �R�V�S�� | ��� |
| �㐽��a�@ | �R�Q�V�� | ��� |
| �s�������s���a�@ | �R�Q�V�� | ��� |
| ���{�ϐ����ؕa�@ | �R�P�T�� | ��� |
| �됶��]�_�o�O�ȕa�@ | �R�O�T�� | ��� |
| ��^��������a�@ | �R�O�P�� | ��� |
| ���[�����a�@ | �R�O�O�� | ��� |
| ��R�a�@ | �Q�X�X�� | ��� |
| ���a��a�@ | �Q�S�R�� | ��� |
| �V���a�@ | �Q�Q�T�� | ��� |
| �k�ۑ����a�@ | �Q�P�V�� | ��� |
| ����s���a�@ | �Q�P�O�� | ��� |
| �������B��a�@ | �P�V�O�� | ��� |
| �����a�@ | �P�T�O�� | ��� |
| �����V�~�Y�a�@ | �P�S�W�� | ��� |
| �O�N�a�@ | �Q�T�� | ��� |
| �����t��a�@ | �P�V�S�� | ���� |
| �m���a�@ | �P�S�O�� | ���� |
| ���|�[����R�a�@ | �P�Q�T�� | ���� |
| �哌�����a�@ | �P�P�V�� | ���� |
�C�O���w�̂�����
���C�̂���Ⴂ�搶�́A�ł������C�O���w�ɍs�����Ƃ����߂Ă��܂��B�@ �ꐶ�U�Ɉ�x�A�C�O�Ő������Ă݂����Ƃ��������R�Ƃ������@�ł������Ǝv���܂��B�C�O�ɍs���Č����̊��ɂ������A�K�R�I�Ɍ����ɖv������悤�ɂȂ�A�����̊y�����A���炵���A�����Č�������������Ǝv���܂��B
�C�O���w�͎����ɂƂ��Ă����łȂ���y�̂��߂ɂ����ɗL���ł��B���Ƃ��A��y�̗��w��̊m�ۂ�A��y�����w�����Ƃ��̕s������_�������̌o����b�����Ƃɂ���ĉ��������A�E�C�t����A�܂��A�����̖ʂł́A�A����������������s�����Ƃɂ���čŐV�̏�����肵�Č�����A�Տ��ɗL�v�ł���Ǝv���܂��B
�����āA�Ō�ɁA��w�̏K���A��͂�A�v���[���e�[�V�����̗͂Ƃ����̂͋ɂ߂ďd�v�ł���Ǝv���܂��B���ېl�ł��邱�Ƃ̏d�v���A�����āA����������̐e�F���C�O�ɂ���Ƃ������Ƃ��A�ꐶ�U�A�|�����̂Ȃ����Y�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�C�O�̘A�g�@��
Harvard�@Medical School�ABritish�@columbia, MD Anderson �Ƃ������A���E�L���̌����@�ւƘA�g�������ċ����������s���Ă��܂��B�����̐��E�L���̌����@�ւɗ��w���A�����̂��炵���A�����āA��������m�邱�ƁA�����āA�A����������������s�����Ƃɂ��ŐV�̏�����肷�邱�Ƃ́A�Ⴂ�搶���̏����ɂ����āA�ɂ߂ċM�d�Ȍo���ƃL�����A�[�ɂȂ�Ǝv���܂��B

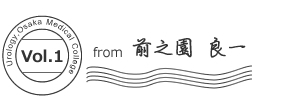
����ȑ�w��2012�N�ɑ��Ƃ����O�V���Lj�Ɛ\���܂��B�������o�g�Ŗ{�w���ƁE�{�w�����Տ����C�C�����2014�N�ɔ�A���B�E���B��w�u�� ��A��Ȋw�����ɓ��ǂ��܂����B
2015�N ���m��Εa�@ ��A��ȏo���A2017�N �ɍ������w�Ƃ��ē������q��ȑ�w ��A��� Clinical fellow���I������A2018�`2020�N Harvard Medical School, Brigham and Women�fs Hospital, Division of Transplant Surgery, Research fellow���I���ċA�����܂����B
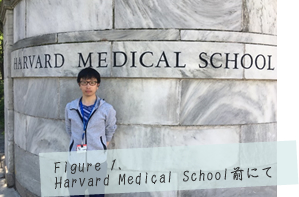 �u��A��Ȃɓ����ăn�[�o�[�h�ɗ��w�����ւv�Ƃ������t�B������w��5�̃|���N��(Poliklinik)�̎��ɓ����̏y�����ł������������̈ꌾ�����ׂĂ̎n�܂�ł����B���nj�A�������̂͂��炢�ŁA�������q��ȑ�w��A��ȂŐt���ڐA���w�тɍ������w���A�����Ă��̌�A���E�ōŏ��ɐ��̐t�ڐA����������Brigham and Women�fs Hospital (������Peter Bent Brigham Hospital)�ɐ��n����A���Ƃ��ڐA�̊�b�������w�тɗ���@��܂���(1954�N��Dr. Joseph E. Murray�ɂ��ꗑ���o�����Ԃ̐��̐t�ڐA�A1990�N�Ƀm�[�x����w�����w���)�B
�u��A��Ȃɓ����ăn�[�o�[�h�ɗ��w�����ւv�Ƃ������t�B������w��5�̃|���N��(Poliklinik)�̎��ɓ����̏y�����ł������������̈ꌾ�����ׂĂ̎n�܂�ł����B���nj�A�������̂͂��炢�ŁA�������q��ȑ�w��A��ȂŐt���ڐA���w�тɍ������w���A�����Ă��̌�A���E�ōŏ��ɐ��̐t�ڐA����������Brigham and Women�fs Hospital (������Peter Bent Brigham Hospital)�ɐ��n����A���Ƃ��ڐA�̊�b�������w�тɗ���@��܂���(1954�N��Dr. Joseph E. Murray�ɂ��ꗑ���o�����Ԃ̐��̐t�ڐA�A1990�N�Ƀm�[�x����w�����w���)�B
���߂Ă̊C�O��l��炵�����鎖�ɂȂ�s���Ɗ��҂����荬����܂������A���������ۂ�Boston�֗��ėǂ��������Ƃ��R������܂����B
��ڂ͌����E�E���E��̒m�荇�������������ł��B�l���m��ň�ÊW�҂Ƃ̕t�������������A�܂��P�ȑ�w�ł������Ƃ����������܂��ē��{�ɂ������͌����҂̕������ƕt�������@��͊�{�I�ɂ���܂���ł����B�u�����O�E�b�h�Œ��H���`Breakfast at Longwood�`�v�Ƃ����A���j�̑���������{�l�����҂��W�܂�R�~���j�e�B�[������A���E��Ƃ̒m�荇�����������������̍��Y�̈�ł��B�n�Ă����ۂ͒N�ł����}�Ȃ̂Ő�������Č��Ă������� (Monday, 6:30am-7:30am, 360 Longwood Avenue, Boston, Massachusetts 02215, Caffe Nero)�B
��ڂ͌����̐�[�ő̊��o�������B���͌������S�҂ł������ׁA���S�ɓ��ɖ��������Ă��܂������O�q�u�����O�E�b�h�Œ��H���v�ŐF��Șb���Ƃ����o���͍���̎����̐i�H�����߂Ă�����Ŕ��ɗL�v�Ȃ��̂ɂȂ�܂����B�����ăA�����J�Ȃ�ł́A�Ƃ������ɂȂ�Ɩc��ȗՏ��ڐA�f�[�^�������@���A�A�����J�̒��ꗬ�a�@�ł���Mayo Clinic�Ń}�E�X�̐S���ڐA�f�����s���@���ꗬ�̉Ȋw�҂̌������ԋ߂ŕ������̕��������铙�A�����Ɋւ��Ă�Boston������Harvard Medical School�ɗ��Ȃ���Ώo���Ȃ������o�����Ǝv���܂��B
�O�ڂ́A����͔��Ƀ��b�L�[�Ȃ��ƂɃA�����J�Ɂu�����v������Ă���ꏊ�����邱�Ƃł����B�n�đO�Ɂu���O��Boston�̊����~�ɌǓƎ����邩�牽����������Ă����v�Ƌ�����...���Ƃ��A�h�o�C�X���Ă��܂������A���܂��܉��h�ƃ��{�̊ԂɌ���������Ă��鏊�����A������2�N�Ԃ����b�ɂȂ�܂����B�����ɂ́u�����m���v�Ƃ������t������܂��B���t�ɂ悭�����m���������Ă����L��������܂����A�����͎����ɖR���������ɗ��ăR�~���j�P�[�V�������\���ɂƂ�Ȃ��łӂƂ��̌��t�������悬��܂����B�u���������Ĉ����ނ�m��v...�ٍ��̒n�ʼn��߂ď��S�ɋA��B
������3�̋@��͖{���Ɏ��ɂƂ��Ă͓��{�ł͂Ȃ��Ȃ�����M�d�Ȍo���ł���A�܂��ɍ���̖��������̊�]�ɂȂ�A�����Ė����̌����Ɍq�����Ă����̂��ȂƎ������܂����B
���͌��݈�t9�N��(2020�N����)�ł���܂����A���E�����̕a�@���o�Ĉ�ʂ�̎����w��ł��܂����B���Ɏ��������N�Ⴂ�q�B���t�s�S�Ŋ����EQOL����������Ă���̂�����ƈڐA��ÁE��ֈ�Â������Ɠ�����O�̑I�����ɂȂ�A���̏�œK�ɑ���z�u���s����悤�ɂȂ�Ώ��Ȃ��Ƃ����ʂ̏��Ȃ���ÂɂȂ�̂ł́A�ƍl����悤�ɂȂ����̂�Boston�ōs���������̎n�܂�ł����B
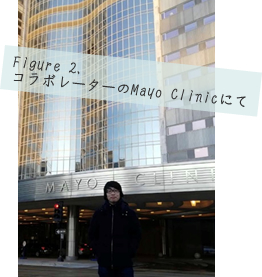 iPS�ɑ�\�����悤�ȍĐ���ÂŐt�����̂��̂����o�����͏�������������������܂��A�ŋ߂ł͓���l�ւ̈ڐA�̕ǂ���蕥����`�q���ҋZ�p��Xenotransplantation (�َ�ڐA)�������Ȃ������ɋ߂Â�����܂��B���̏������Ă������{�͎c�O�Ȃ��炱�����������͍s���Ă��܂���ł������A�K�ȑ���z�u���ł��Ȃ����ɂ��ċ����������A���݂͐��ʂ�aging�ɗ��߂��e�[�}�ňڐA�̌������s���Ă���܂��B�ȒP�ɏq�ׂ�ƃ��V�s�G���g�ƃh�i�[�̐��ʂ�aging�ɔ����j���̃z��������ԂŐ��т��قȂ�̂��A���ꂼ��ɍ���������z�u���o����悤�ɂȂ�A�Ǝv�����������ĎQ��܂����B
iPS�ɑ�\�����悤�ȍĐ���ÂŐt�����̂��̂����o�����͏�������������������܂��A�ŋ߂ł͓���l�ւ̈ڐA�̕ǂ���蕥����`�q���ҋZ�p��Xenotransplantation (�َ�ڐA)�������Ȃ������ɋ߂Â�����܂��B���̏������Ă������{�͎c�O�Ȃ��炱�����������͍s���Ă��܂���ł������A�K�ȑ���z�u���ł��Ȃ����ɂ��ċ����������A���݂͐��ʂ�aging�ɗ��߂��e�[�}�ňڐA�̌������s���Ă���܂��B�ȒP�ɏq�ׂ�ƃ��V�s�G���g�ƃh�i�[�̐��ʂ�aging�ɔ����j���̃z��������ԂŐ��т��قȂ�̂��A���ꂼ��ɍ���������z�u���o����悤�ɂȂ�A�Ǝv�����������ĎQ��܂����B
�u���߂悳��Η^����v...�܂��Ɍ��݂̑���Ȗ�ȑ�w �t��A��O�Ȃ�\���Ă���Ǝv���܂��B��A��Ȃɋ����������ł������Ă���搶���A���Ȃ͌Q���ĖZ�����ł������̕��`�����X�͋��߂�ǂ������L����܂��B�l���͈�x��������܂���B�ꐶ�Ɉ�x�A�C�O�Ŋ��Ă݂܂��B
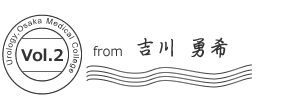 2012�N���̋g��@�E��ł��B
2012�N���̋g��@�E��ł��B
2017�N�S������2020�N�R���܂ł̎O�N�ԁA�A�����J�A�j���[���[�N�A�}���n�b�^���ɂ���Memorial Sloan Kettering Cancer Center�Ŋ�b���������Ă��܂����B
�����m�̒ʂ�A�j���[���[�N�͓����ł��ő�K�͂̓s�s�ŁA���̐l����800���l���Ă��܂��B�ݕē��{�l�����s�s�����Ŗ�T���l�A�B�ł͖�10���l�𐔂���ƌ����Ă���܂��B�uBig Apple City�v��uNon-Sleeping City�v�Ȃǂ̈��̂Œm���Ă���A���E�o�ς̒��S�n�̈�s�s�A��y�⊈���̖��͂ƂȂ��s�s�ł��鎖�͊ԈႢ����܂���B

���{�ł́u�������O���B���ɑ���V�K���Áv�Ƃ����e�[�}�ŁA������R�����l�������O���B���ɂ����āA��`�q���x���ł̎��Â��s�����Ŋ����̖�̌��ʂ����コ���鎖��ړI�Ɍ������s���Ă���܂����B
���{�ł͖w�NJ�b�����̌o�����Ȃ��������ɂƂ��ẮA�������Ă������{�̃����o�[�̐^�����Ⓖ�������A�^�����͐V�N�ŁA����������ɐG�ꎩ�g���������邫�������ɂȂ������͊ԈႢ����܂���B
�܂��A���̏������Ă������Z���^�[�͕a�@�Ƃ��Ă������{�݂Ƃ��Ă��L���ł���A���E�������t�A�����҂����ǂ��������߂ďW�܂��Ă���܂����B���{�l����O�ł͂Ȃ��A�e��w�̐搶�������X�ƏW�܂�A���̕��X�ƌ𗬂����A�e����[�߂�ꂽ�͍̂���̎����ɂƂ��đ傫�ȍ��Y�ƂȂ�܂����B
�C�O�o�������Ȃ������������w���Ďv�����̂́A�u�C�O�͉�������ǁA�߂��v�Ƃ������ł����B���R�̎��������Ă���悤�ł����A���ꂪ�p��A���s���l�����{�l�ł͂Ȃ��A�ʉ݂��h���A����ȊO�͓��{�Ƒ傫���ς��Ȃ������𑗂��Ă���ƍl����Ɖ��̂��s�v�c�Ȋ��������܂����B

- �j���[���[�N�̓A�p�����E�t�@�b�V�����Ƃ�ό��ƁA�X�|�[�c������ȊX�ł��B����C�A�V���b�s���O�ɋ�����������A�u���[�h�E�F�C�~���[�W�J����W���Y�A�~���[�W�A���ɋ�����������A
��@���@�@�@�@�@�i�j���[���[�N�E�����L�[�X�A�j���[���[�N�E���b�c�j�A
�o�X�P�b�g�{�[���i�j���[���[�N�E�j�b�N�X�A�u���b�N�����E�l�b�c�j�A
�A�C�X�z�b�P�[�@�i�j���[���[�N�B�����W���[�X�A�j���[���[�N�E�A�C�����_�[�X�j�A
�����ăA�����J���t�b�g�{�[���i�j���[���[�N�E�W�F�b�c�A�j���[���[�N�E�W���C�A���c�j�ɋ�����������A
�S�Ă̐l����������������Ă���܂��B

�j���[���[�N���班�����������A�t�B���f���t�B�A��V���g��������j���[���[�N�Ƃ͈�����X���݂��y���߂܂��B�������y���݂������̓A�g�����e�B�b�N�V�e�B�ɍs���̂��ǂ��ł��傤�B�܂��A�{�X�g���A�n�[�o�[�h�ɂ͎��B�̈�ǂ��瓯����̐搶�����p���I�ɗ��w���Ă��艽�x���K��܂����B���{�ňꏏ�ɓ����Ă������ɉ�̂Ƃ͎������A�ł��A�����悤�ȕ��͋C�𖡂키�����ł��A���Ɋy�������Ԃ��߂����܂����B
�����A�u��b�������������v�A�u���w�ɍs���Ă݂����v�ƍl���Ă�����̐搶������������Ⴂ�܂�����A�u�����͍s�������I�v�ƐϋɓI�ɐ��ɏo���ĉ������B
�V�������ɒ��킷��̂ɂ́A�E�C�ƃp���[���K�v�ł��B�ł����A����ݏo���Ă݂ĉ������B��������ΊԈႢ�Ȃ��A�����ɂƂ��ĉ����̌o�����܂��B
���ɂƂ��Ă��̗��w���Ԃ͐l���̒��ōł��M�d�ȎO�N�Ԃł������Ǝv���܂��I�I
��A��Ȃ��l���Ă��錤�C��̐搶����
��A��Ȃƕ����Ɛ��a��j�����B���f��Ȃ��C���[�W����w������⌤�C��̐搶�������Ǝv���܂��B�m���ɁA��������A��Ȉ�͒j�����B���s�����ǂ������܂����A����f�Âł��̊�����1�������Ƃ����Ƃ���ł��B���ۂ̌���ł͔A�H������ᇁA�r�A��Q�A�t�s�S�A�A�H���A�A�H�����Ȃǂ̎������قƂ�ǂł��B
 ���Ɉ�����ᇂ�r�A��Q�͒�����Љ�ɓ˓����Ă�����{�̍�����l����Ɖv�X�����Ă����Ɨ\�z����A���ۂɑO���B���ǂ͍ŋ�15�N�Ŗ�3�{�ɑ����Ă��܂��B�������Љ�ɂȂ�ƍ������A���A�a�A�S�؍[�ǁA�]���ǎ������������Ă������Ƃ��\�z����܂����A�����ɗ\�h��w�����W���Ă������ߑ��ΓI�ȑ����͏��Ȃ���������܂���B�A�H������ᇂ�O���B���ǂ͗\�h������ȕa�C�ł���A���̐��A��Ȉ�̎��v������ɍ��܂�͖̂ڂɌ����Ă��܂��B
���Ɉ�����ᇂ�r�A��Q�͒�����Љ�ɓ˓����Ă�����{�̍�����l����Ɖv�X�����Ă����Ɨ\�z����A���ۂɑO���B���ǂ͍ŋ�15�N�Ŗ�3�{�ɑ����Ă��܂��B�������Љ�ɂȂ�ƍ������A���A�a�A�S�؍[�ǁA�]���ǎ������������Ă������Ƃ��\�z����܂����A�����ɗ\�h��w�����W���Ă������ߑ��ΓI�ȑ����͏��Ȃ���������܂���B�A�H������ᇂ�O���B���ǂ͗\�h������ȕa�C�ł���A���̐��A��Ȉ�̎��v������ɍ��܂�͖̂ڂɌ����Ă��܂��B
�Ȃ̑I���ɂ̓��[���͑��݂��܂���B�I�����闝�R����������肪����܂��A���C�オ�l����̂́u�d�����e�v�u�����v�u�Ζ����ԁv�u�l�ԊW�v��4�ł��傤�B�����A�Ζ����ԁA�l�ԊW��1�l�O�ɂȂ�Όl�̔\�͂ł�����x���P���邱�Ƃ��ł��܂�(������Ȃ͂���3���ׂĂɂ����đ��Ȃɗ���Ă���Ƃ͎v���܂���)�B�������A��͂�d�v�Ȃ͎̂d�����e�ł��B
 ��A��Ȃ͊O�ȓI���ʂƓ��ȓI���ʂ̂���Ȃł��B������ᇁA���A�O���B���ǂɑ����p�͔N�X�������Ă���A�O�Ȍn�̒��ł��ł���������p�����B���Ă���Ȃł��B���ɍŋߘb��ɂȂ郍�{�b�g��p�ɂ����Ă͕���24�N4�����݁A�ی��K���ɂȂ��Ă���͈̂����O���B��p�݂̂ŁA�O�ȕ���̐�삯�Ƃ����܂��B���ȓI���ʂ͔A�H�����A�t�s�S�Ƃ������S�g�Ǘ���K�v�Ƃ��鎾�����������Ƃł��B���ɖ����t�s�S�̎��Âł͌��t���͂╠�����͂������Ȃ��S�g�Ǘ�������K�v������܂��B
��A��Ȃ͊O�ȓI���ʂƓ��ȓI���ʂ̂���Ȃł��B������ᇁA���A�O���B���ǂɑ����p�͔N�X�������Ă���A�O�Ȍn�̒��ł��ł���������p�����B���Ă���Ȃł��B���ɍŋߘb��ɂȂ郍�{�b�g��p�ɂ����Ă͕���24�N4�����݁A�ی��K���ɂȂ��Ă���͈̂����O���B��p�݂̂ŁA�O�ȕ���̐�삯�Ƃ����܂��B���ȓI���ʂ͔A�H�����A�t�s�S�Ƃ������S�g�Ǘ���K�v�Ƃ��鎾�����������Ƃł��B���ɖ����t�s�S�̎��Âł͌��t���͂╠�����͂������Ȃ��S�g�Ǘ�������K�v������܂��B
10�N��A20�N��ɋ��߂����Â��ǂ�Ȃ��̂���z�����Ă��������B�����Ə��q���A������̐i��ł�����{�ł͘V�l��Â����S�ɂȂ��Ă���͂��ł��B��A��Ȃ͂��̒��S�Ƃ͂����܂��A���̎�v�ȕ���̂P�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��傤�B�K���A���M�ƌւ�������Ďd�����ł���ƐM���Ă��܂��B