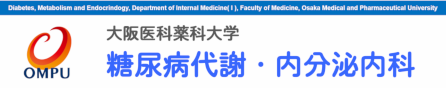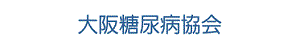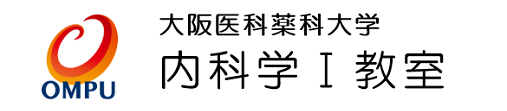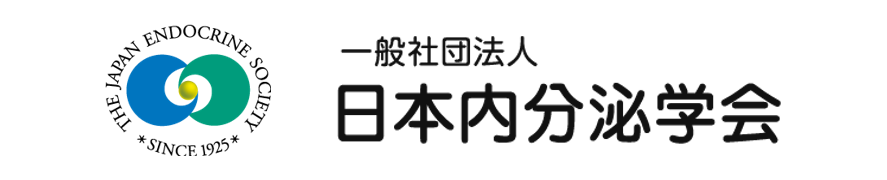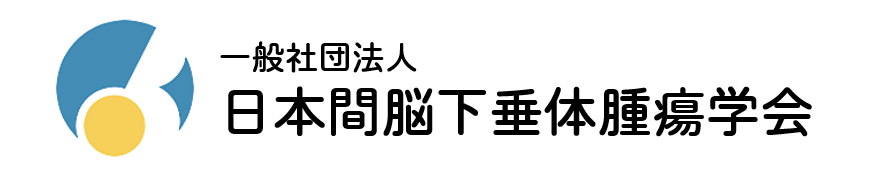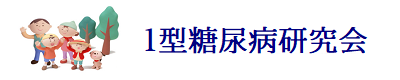- ホーム
- 診療内容
診療内容
糖尿病代謝・内分泌疾患は全身疾患であり、様々な合併症を引き起こすことが特徴です。当科では単に対象疾患の管理を行うだけでなく、他科と連携しながら、患者の立場に立った全人的医療を実践することを基本理念としています。
当科の対象となるのは、
1)糖尿病などの糖代謝異常、高脂血症などの脂質代謝異常、痛風などの核酸代謝異常といった代謝異常を主病態とする疾患、
2)甲状腺、下垂体、副腎、副甲状腺などの内分泌臓器の異常を主病態とする疾患。また、近年注目されているメタボリック・シンドロームや肥満症など、複合的な代謝・内分泌異常を伴った疾患も対象としています。
診察は、3診体制で専門外来を行っており、主に糖尿病代謝疾患は2診で、内分泌疾患は1診で診察にあたっています。
診療体制について
糖尿病専門外来
当院では2型糖尿病をはじめ1型糖尿病や妊娠糖尿病に対して食事・運動療法から最新の薬物治療、また合併症に至るまで幅広く診療を行っています。その中で血糖コントロールが不安定な1型糖尿病患者さんやコントロール不良の2型糖尿病患者さんための糖尿病強化外来を開設しており、持続血糖測定(CGM:Continuous Glucose Monitoring)やインスリン皮下持続注入(CSII:Continuous Subcutaneous Insulin Infusion)やSAP(Sensor-Augmented Pump)の外来・入院での導入も行っています。また最近では先進糖尿病治療デバイスの導入も積極的に行っています。
糖尿病フットケアを含む糖尿病看護外来を常時開設しており、インスリンの自己注射に関連する療養指導や足の観察・洗い方・爪の切り方など、糖尿病患者さんとその家族の方と一緒に行い、糖尿病合併症の予防や早期発見に努めています。

CGM:血糖持続測定
内分泌専門外来
「ホルモン」は内分泌腺で産生・分泌され、全身の様々な臓器に運ばれて作用を示します。内分泌腺として、下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、性腺などが知られています。
内分泌専門外来では、「ホルモン」が多すぎたり、少なかったりすることで生じる疾患を中心に診療を行っています。
下垂体疾患:
下垂体は前葉と後葉の2つの部分からなります。前葉は6種類のホルモン(副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、成長ホルモン(GH)、黄体化ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、プロラクチン(PRL))を、後葉は抗利尿ホルモン(ADH)とオキシトシンを分泌します。これらのホルモン分泌が過剰であるか、それとも低下しているかを的確に診断し、治療を行っております。
・下垂体ホルモンの分泌低下(下垂体機能低下症)が疑われた際には、下垂体ホルモン基礎値、およびホルモン負荷試験(刺激試験)を行うことにより、ホルモン動態をより正確に把握し治療方針の決定に役立てています。下垂体機能低下症における治療は数種類のホルモンを同時に補充することが多く、より細やかな診療が必要です。
・ホルモン産生性下垂体腺腫により、下垂体ホルモン分泌が過剰になることがあります。GH分泌過剰は先端巨大症、ACTH分泌過剰はクッシング病、PRL分泌過剰はプロラクチノーマ、TSH分泌過剰はTSH産生腫瘍と呼ばれ、薬物、手術もしくは放射線治療が必要な疾患です。検査により、過剰な下垂体ホルモンを的確に評価し、内科的な薬物治療を行っています。さらに、手術治療が必要と判断した場合には、脳神経外科と協力して治療を行っています。
(主な疾患:下垂体機能低下症、成人成長ホルモン分泌不全症、尿崩症、先端巨大症、クッシング病、プロラクチン産生下垂体腺腫、TSH産生下垂体腺腫、リンパ球性下垂体炎、IgG4関連下垂体炎、免疫☑ポイントによる下垂体炎、SIADH(ADH不適切分泌症候群))
甲状腺疾患:
甲状腺は甲状腺ホルモンを分泌する臓器です。甲状腺ホルモンの増加、減少、および甲状腺にできる腫瘍に対して診療を行っております。
血液検査、および甲状腺超音波検査をすることにより的確に診断するよう努めています。また、甲状腺腫瘍については、必要に応じてエコー下での穿刺吸引細胞診を施行して治療方針を決定しています。
(主な疾患:バセドウ病、橋本病、甲状腺機能低下症、無痛性甲状腺炎、亜急性甲状腺炎、甲状腺腫瘍、他)
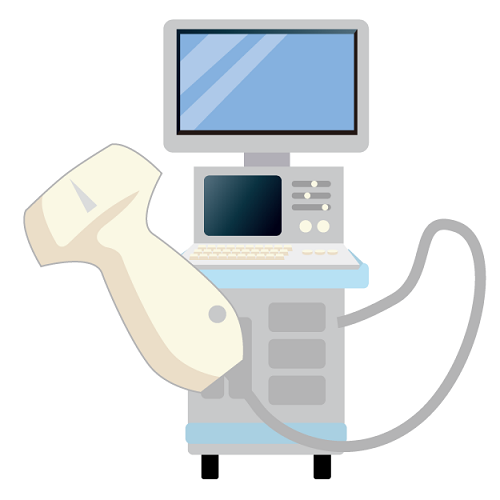
甲状腺超音波検査
副甲状腺疾患、骨疾患:
副甲状腺は副甲状腺ホルモンを産生し、血液中のカルシウム濃度を調節しています。副甲状腺ホルモンが過剰になると血中カルシウム濃度は上昇し、骨のカルシウムが溶け出して骨粗鬆症、尿路結石などを起こします。これは、副甲状腺に腫瘍ができることにより起きることが大半です。血液検査、尿検査、超音波検査、さらにMIBIシンチを組み合わせ、的確に診断できるよう努めています。
(主な疾患:副甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能低下症、骨軟化症、骨粗鬆症)
副腎疾患:
副腎は、コルチゾール、アルドステロン、アンドロゲンを産生する副腎皮質と、カテコールアミンを産生する髄質からなる臓器です。これらのホルモンが過剰になると、高血圧、糖尿病など様々な症候、合併症をきたします。副腎にできた腫瘍がホルモンを過剰に産生することが多く、コルチゾール過剰を来すクッシング症候群、アルドステロン過剰を来す原発性アルドステロン症、カテコールアミン過剰を来す褐色細胞腫などがあります。これらの疾患に対し、ホルモン評価だけでなく、CT・MRI検査、アドステロールシンチやMIBGシンチなどのRI検査、副腎静脈サンプリングなど、各種検査を総合して診断・治療を行っています。さらに、手術治療が必要と判断した場合には、泌尿器科と協力して治療を行っています。
(主な疾患:クッシング症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、副腎腫瘍、アジゾン病、先天性副腎皮質過形成)
外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (第1・3・5) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 細井 稲葉 中嶋 |
金綱 稲葉 渡邉 |
今川 長江 峠 |
寺前 佐野 深尾 |
今川 荘野 藤澤 |
担当医 吉田 |
| 午後 |
稲葉 1型糖尿病ポンプ外来 大西(4) |
藤澤 GDM外来 山村(1,3,5) 中嶋(2,4) |
長江 吉田(2,4) SAP・CSII外来 大西(1,3,5) |
佐野 細井 堤 |
寺前 金綱 山村 |
|
| ※GDM=妊娠糖尿病 ※SAP= パーソナルCGM付きの持続皮下インスリン注入療法 ※CSII=持続皮下インスリン注入療法 | ||||||
| 【病院HPの外来担当表】 | ||||||
看護専門外来(糖尿病関連のみ掲示)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 (第1・3・5) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 糖尿病 療養指導士 |
糖尿病 療養指導士 |
糖尿病 療養指導士 |
フットケア 療養指導士 |
||
| 午後 | 糖尿病 療養指導士 |
糖尿病 療養指導士 |
糖尿病 療養指導士 |
糖尿病 療養指導士 |
糖尿病 療養指導士 |
入院について
糖尿病センター(78病棟)を中心に診療を行っています。糖尿病教育入院やインスリン注射の導入、また糖尿病合併症の加療目的の患者さんが入院されています。
なかでも、医師・看護師・栄養士・薬剤師・理学療法士・臨床心理士・検査技師らによる‘大阪医科薬科大学病院糖尿病ケアチーム OMC-DCT’ の専門スタッフによる糖尿病教育コース(1週間のプログラム)は、患者さん自ら積極的に治療に取り組む自己啓発の機会として重要な役割を果たしており、「糖尿病のトータルマネージケア」を目指しています。
この他にも他科での治療(外科周術期、妊娠、ステロイド治療など)に際して、全科的に糖尿病代謝・内分泌疾患を有する患者さんの管理を行っています。
その他の特徴について
病診連携システム
高槻市医師会などと共同で糖尿病地域連携パスの作成にあたり、平成19年11月より高槻市医師会地域連携クリティカルパス「糖尿病」として運用が開始され ています。現在、このパスを有効活用しながら、地域における医療連携と糖尿病診療のレベルアップに寄与すべく、定期的に実地医家との研究会や勉強会を開い ています。
特定機能病院としての先進医療
血糖持続モニタリングシステム(CGMS) や人工膵臓などを用いた糖尿病の病態把握、インスリンポンプ・CSII(持続皮下インスリン注入)療法なども行っています。また、1型糖尿病の約2割をし める劇症1型糖尿病については、糖尿病学会調査研究委員会の事務局として日本における診療の中心的役割を担っており、当院通院中の患者さんの診察だけでは なく、セカンドオピニオンを求めて遠方から来院される患者さんの診療、学会調査活動、マスコミを通した広報活動などを行っています。
全人医療
当科の対象とする疾患は慢性疾患が多く、精神的なケアを含めた全人的なアプローチが必要である。当科では心療内科や漢方も取り入れた全人的医療にも取り組んでいます。
他科との連携
代謝疾患を合併する疾患に対応するため、循環器内科、神経内科、心臓血管外科、皮膚科、形成外科、整形外科、眼科、泌尿器科、血液浄化センター等と緊密な 連携をとり、特定機能病院として、他の施設では治療が難しい患者さんの治療にあたっています。
内分泌疾患については、内分泌検査及び画像検査による的確な診療と治療方針の決定を行っており、外科的治療の適応については局在診断後、当該診療科との連 携を密に取り、周術期の管理及び術後のフォローアップに当たっています。特に、甲状腺腫瘍については穿刺吸引細胞診を施行し、手術適応症例については当院 耳鼻科および当科関連施設と連携をして対応しています。
NSTへの参加
栄養学に関わりの深い代謝疾患を専門とする立場から、院内NST(Nutrition Support Team)にも積極的に参加しています。➡NSTのHP
その他
糖尿病患者会である「若槻会」(大阪糖尿病協会支部)を通じて、会報誌の発行やイベントなどを開催し、患者さんとの交流と情報交換が行われています。
入院患者実績(2023年度)
| 患者数 | 内 訳 | |
|---|---|---|
| 糖尿病 | 334 | 2型糖尿病234例、1型糖尿病40例、妊娠糖尿病30例、その他30例 |
| 甲状腺疾患 | 13 | バセドウ病7例、橋本病6例 |
| 間脳下垂体疾患 | 30 | 下垂体機能低下症8例、ACTH単独欠損症5例、中枢性尿崩症7例、下垂体腫瘍7例、その他3例 |
| 副腎疾患 | 15 | 原発性アルドステロン症3例、クッシング症候群2例、服腎不全7例、褐色細胞腫3例 |
| その他の疾患 | 39 | DKA6例、HHS10例、低血糖2例、肥満症4例、他17例 |
当院のクリニカルインディケータ(2022年度)