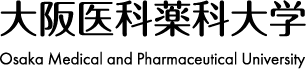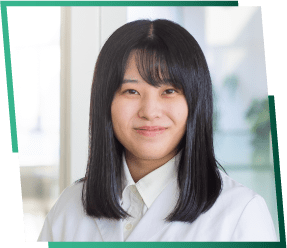覚えるから、考える学びへ。 薬剤師に近づいていることを実感。
薬学部 第4学年井上 麻里萌 さん
- 現在、どのようなことを
学ばれていますか? - これまでは主に基礎的な薬学の知識について勉強してきましたが、4年次ではそれに加え、薬剤師や医薬品に関する法律なども学びます。また、症例を見てすでに覚えた知識を生かして自分で考えてみたり、添付文書などを調べて患者さんにあった薬を考えたり、今までに比べて覚える学びから考える学びにシフトしてきました。コミュニケーションや調剤、チーム医療などについても学ぶ機会があり、より臨床に近づいてきたのを日々実感しています。

- 薬学共用試験に向けてどのように
取り組みましたか? - 薬学共用試験には、知識を問われる「CBT」と実技が評価される「OSCE」があり、いずれにも合格しなければ5年次の臨床実習に行けません。「CBT」のテスト範囲は4年次までに勉強した全範囲なのでかなり不安でしたが、少しずつ復習していくことで自信を持って試験に臨めました。「OSCE」については、実習で調剤の手技やコミュニケーションの仕方を、先生が見てアドバイスしてくださるので、それらをしっかりと吸収して自分のものにしていきました。

- 研究室ではどのようなテーマについて
研究を
進めていますか? - 私は衛生化学研究室に所属しています。この研究室を選んだ理由は、元々、肥満や生活習慣病について興味があり、研究内容を見て「ダイエットの研究みたいで面白そう!」と思ったからです。さまざまな研究テーマがある研究室ですが、私はブロッコリースプラウトに含まれる成分を接種することで、脂肪細胞に溜め込む脂肪の量を減らせるのか、その時に細胞内でどんな変化が起こっているのかについて研究を進めています。

- 大阪医科薬科大学の薬学部の魅力は
どこだと思いますか? - 勉強のモチベーションを保てる、とても良い環境が本学の魅力だと思います。普段はみんなワイワイ楽しく過ごしていますが、「やる時はやる!」とスイッチの切り替えが上手くできる人がとても多いです。試験が近づくにつれてラウンジや図書館、自習室で勉強をする人が自然と増えていきます。勉強に疲れて周りを見渡すと、他の学生が真剣に勉強しているので「私も頑張らなければ」という気持ちになります。
井上さんの時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 9:00-10:30 | 個別化医療 | 薬学基礎 演習 |
薬学基礎 演習 |
||
| 2限 10:40-12:10 | 連携 医療学 |
||||
| 3限 13:00-14:30 | コミュニティ ファーマシー |
臨床導入 学習2 |
研究室 | ||
| 4限 14:40-16:10 | 研究室 | ||||
| 5限 16:20-17:50 |
※時間割は一例であり、実際とは異なる場合があります。
学びのステップ
- 入学前
- 父が薬剤師で、幼い頃から薬に興味がありました。薬学部進学を決めたのは高校生の頃です。自分が薬を飲んだ時に、「たった1錠、こんなに小さいのにここまで効くなんてすごい!」と感動し、私も薬について本格的に学んでみたい、薬の面から患者さんをサポートしたいと思ったのがきっかけです。
- 1〜2年次
- 元々、化学が好きだったのですが、入学してから根本的な原理や知識を深く学べ、より一層好きになりました。薬学部では化学と生物の知識を使うことが非常に多く、自分が苦手な範囲でも粘り強く覚えないといけないため、忍耐力や集中力がついたと思います。大変でしたが、薬学の基礎をしっかり学ぶことができました。
- 3年次〜現在
- 1・2年次までの学びは、どちらかと言うとバラバラの知識をひたすら頭に詰め込んでいく感じでしたが、3年次からはその知識がつながっていくことが増えました。新しい知識が出てきても、今までの知識を振り返って「だからこうなるのか」と理解して勉強するようになったことで、知識の定着が進みました。
- 将来の目標
- 単に薬を渡してくれる人ではなく、「相談しやすいし、気になることや分からないことがあったらとりあえずこの人に聞いてみよう」と思ってもらえる薬剤師になるのが目標です。そのためにも、5年次の臨床実習では、先輩薬剤師さんたちのコミュニケーションの取り方やスキルを学んでいきたいと思っています。