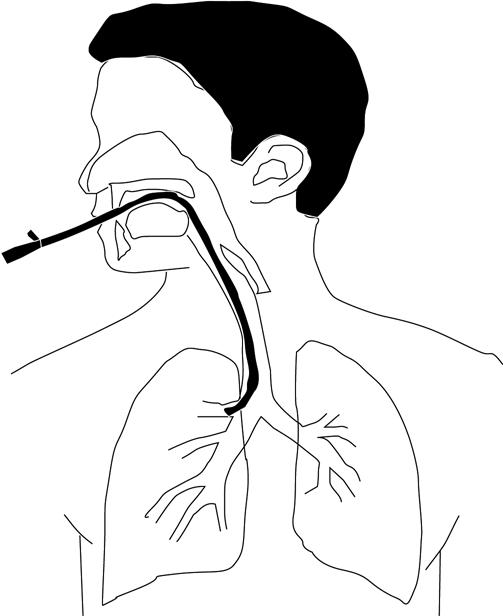 図2
図2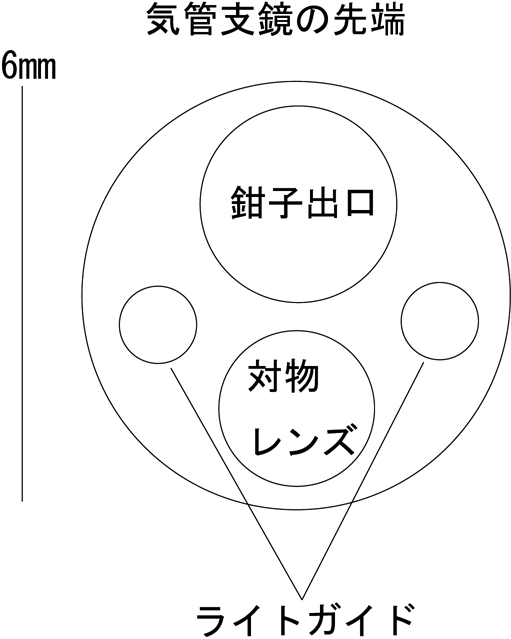
図1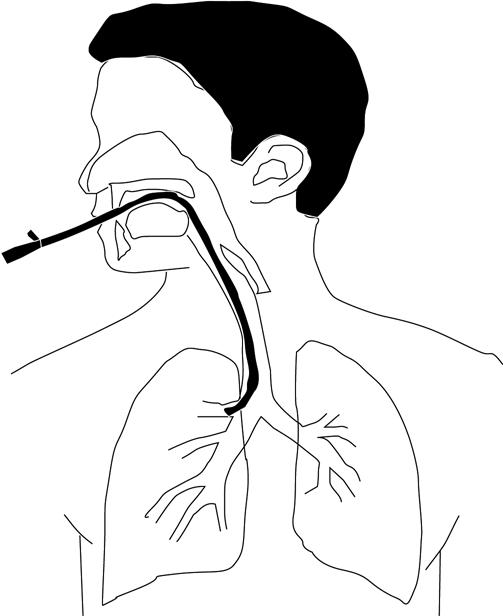 図2
図2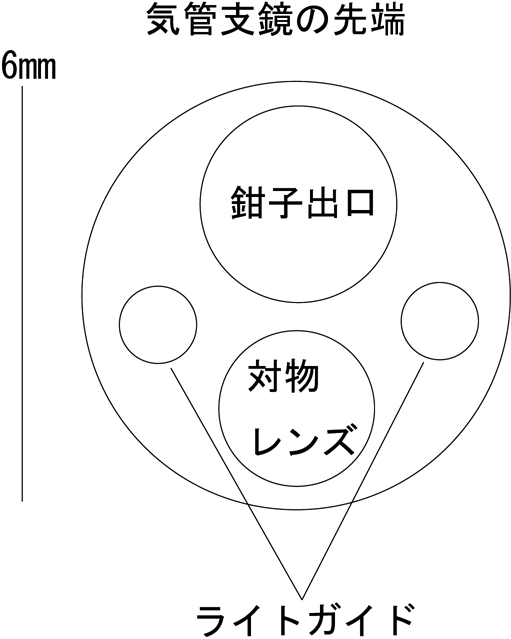
図3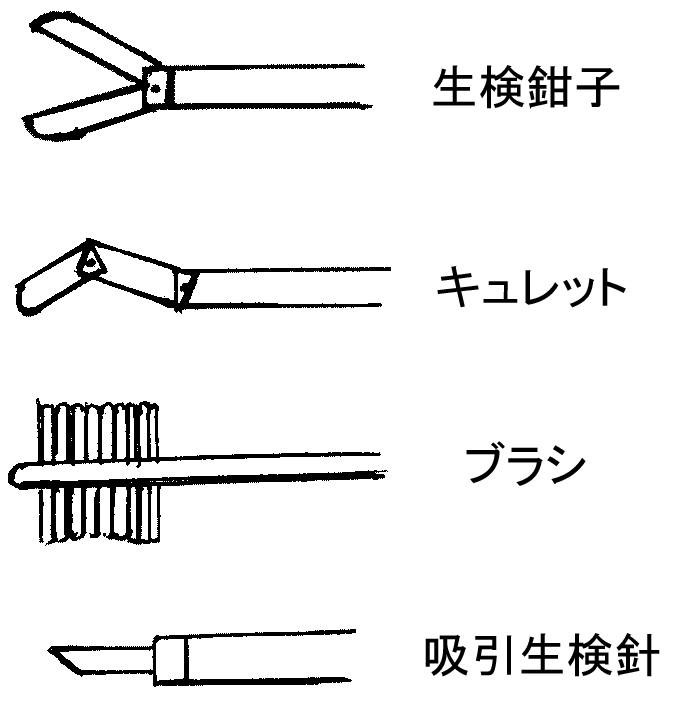
生検、擦過等の処置が必要な場合(ほとんどの場合が相当します)は、脳梗塞、狭心症その他の病気の場合よく処方される薬ですが、血を固まりにくくす る薬または血をさらさらにする薬(たとえば、ワーファリン、アスピリン、パナルジンなど)は前もって中止する必要があります。検査を受ける前に申し出てく ださい。
当日は直前の食事が絶食になります(午前中の検査の場合朝食抜き)が、血圧の薬、狭心症の薬などは飲んでおいたほうが良い場合が多いですので前 もって内服薬を教えてください。
検査に出る前に入れ歯のある場合は外しておいてください。検査中に紛失する可能性もあります。
検査に先立って、まず唾液、痰などの分泌物を減らす薬(硫酸アトロピン)と鎮静剤(ペンタジン)を筋肉注射します。心臓の病気、緑内障、前立腺肥 大のある方は、薬剤の変更が必要になる場合があります。
つぎに局所麻酔剤(キシロカイン)でのどと気管の麻酔を行います。咽頭反射(のどを刺激したとき”オエッ”とむかつきがでる反射)と咳反射(むせ て気管にものが入ったときに咳がでる反射)を押さえるのが目的です。苦い液ですが、霧吹きのようにして麻酔薬を噴霧します。のどに吹き掛けることとで咽頭 の麻酔をし、局所麻酔薬を呼吸に合わせて吸うことで気管の中まで麻酔をします。また検査中も適宜麻酔を追加します。
以上が伝統的な麻酔方法ですが、息をするところにファイバーが入りますので苦しい検査といわれてきました。このため最近はほとんどの方で静脈麻酔を
行うようになりました。つまり点滴をしながら横から麻酔薬(ドルミカム)を注射して眠った状態で検査を受けてもらっています。もちろんある程度の呼吸抑制
はありますので、酸素吸入と酸素飽和度のモニターをしながら行います。このため準備に時間がかかること、検査中の事はほとんど覚えていない人が多い(麻酔
薬による健忘:検査中の事を全く覚えていない場合もあること)など問題点はありますが、楽に検査を受ける事ができます。ただし静脈麻酔を希望しない場合
は、希望に従いますので主治医に相談してください。
図4
気管支鏡検査はほとんどが安全に行える検査ですが、合併症のある場合危険な場合が有ります。このため前もって心電図、血液ガス、止血機能などで検
査を行うにあたって注意すべき病気がないか確認します。
しかし基礎疾患や合併症がない場合でも副作用や合併症は起こることがあります。
1)麻酔に伴う副作用
通常は問題なく局所麻酔を行うことが可能ですが、まれに局所麻酔薬(キシロカイン)の中毒症状として血圧低下、意識混濁、痙攣、不随運動を起こす
ことがあります。いずれも一過性でほとんどの場合、短時間で回復します。
麻酔薬のアナフィラキシーショック(薬に対するアレルギー反応による突然の血圧低下)は、1万人に約1.5人の頻度で起こり得ます。
2)出血
組織検査のために検体を採取する際に出血が認められることがあります
検査後、血痰が認められることが多いですが、多くの場合、自然にとまりますが長くても1週間ぐらいで止まります。
ごくまれに緊急処置が必要となる大量の出血が認められることがあります
3)発熱
検査当日に38℃前後の発熱を認めることがありますが多くは翌日には解熱します。翌日以降も発熱が続く場合には、肺炎を合併していることがありま す。
4)咽頭痛
検査後、のどの違和感や痛みを認めることがありますが、一過性であることがほとんどです。
5)気胸
経気管支肺生検の際に肺をおおっている胸膜に穴があき、気胸(胸腔内に空気が入り肺が縮むこと)を起こすことがあります。ほとんどは症状を伴わず 自然に回復しますが、咳、呼吸困難が出現することもあります。程度がひどい場合は肺を広げるために胸腔にトロッカーという管をいれることが必要になること もあります。
6)呼吸困難
間質性肺疾患の病気の種類によっては、気管支肺胞洗浄後に増悪が起こることがあります。